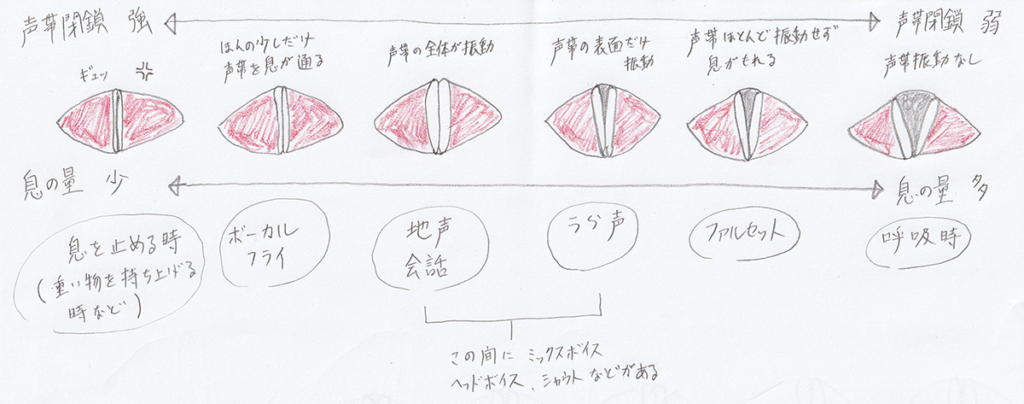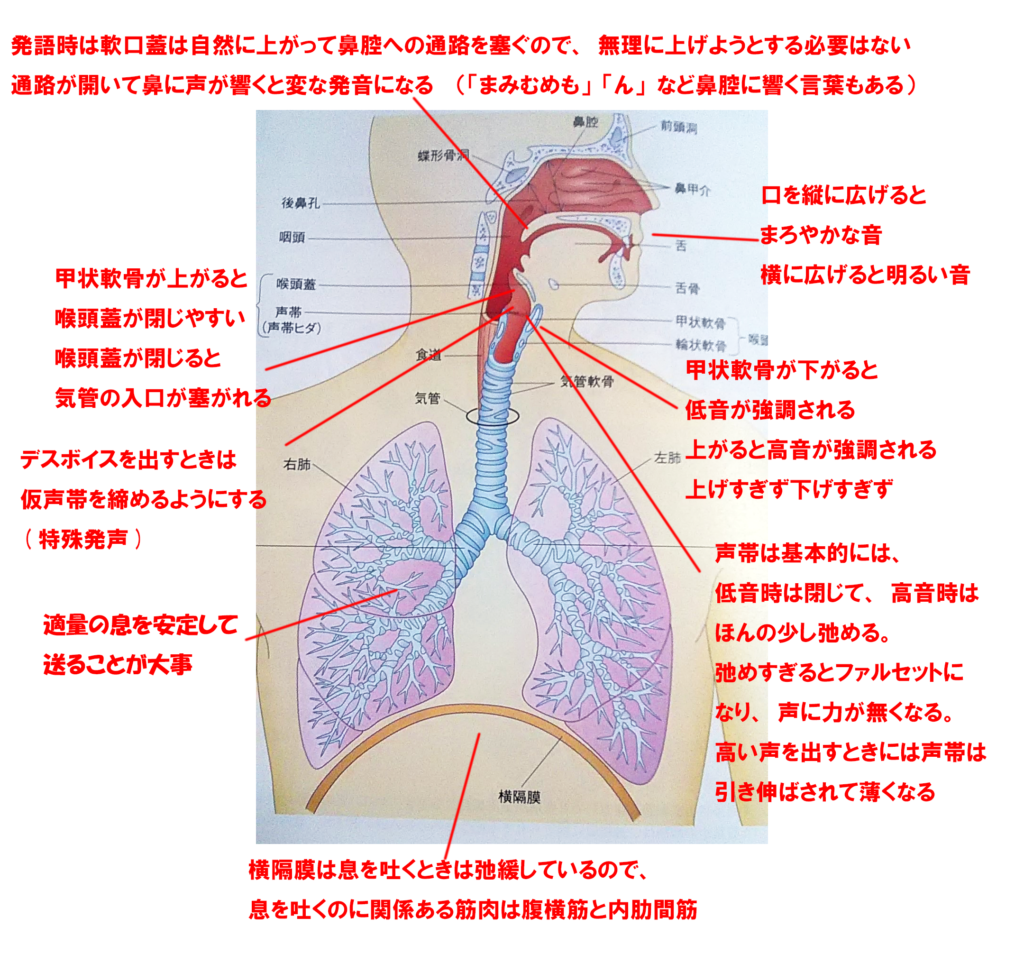今回のまとめ
・リップロールで歌うと「呼吸」と「声帯閉鎖」の練習になる
・バックプレッシャーがかかって声帯振動が整う(らしい)
・一定の量の息を安定して出す練習になる
・声帯閉鎖が強くて、地声で力んでしまう人に良い
・声帯閉鎖が弱い人には逆効果かもしれないので注意
前回の記事で「ボイトレでやるべき事は個人個人で違う」と書きましたが、最初のうちは「コレやっとけば、だいたい間違いない」という練習方法があります
(あくまで私が個人的に考えることなんですが、、、)
それはリップロールです
リップロールしながらメロディを歌うんです
・・・なんだよ、そんな単純な事かよ!と思うかもしれません
しかし、目的意識をもってリップロールするのが大事なんです
一番最初の記事にも書きましたが、歌の上達は 呼吸・声帯・共鳴を自在にコントロールできるようになることです
リップロールはこの中で一番難しい「呼吸」と「声帯の閉鎖」の改善に役に立ちます
しかもこの練習は声帯への負担も少ないです
声帯閉鎖のコントロールでも書きましたが、地声から裏声に上手く移れないのは、声帯の閉鎖が強すぎるパターンが多いです(中にはその反対の人もいますが)
声帯の閉鎖が強いということは、息を吐けてません
逆に息を吐けるということは、声帯閉鎖が弱いということ
ならばリップロールで息をしっかり吐きながら歌うクセをつければ、声帯の閉鎖も弱まるのでは?という発想です(この方法で何人か実験して上手くいってます)
例えばですが、地声で吐いてる息の量が「5」だとします
ため息で吐く量が10、息を止めると0とします
数字が多いほど、肺から出る息の量が増えます
ため息 10
ファルセット 8
裏声 7
ミックスボイス 6
地声 5
力んだ地声 4
ボーカルフライ 1
息を止めている 0
声帯閉鎖が強い人は、閉鎖が強いために4~5の量の息しか吐けません
リップロールで歌っているときは7~8の量の空気が声帯を通過します
7~8の空気の量を出す感覚に慣れると、普通に歌ったときに5.5くらいに落ち着きます(笑)
5.5って微妙な数字ですが、5→6のミックスボイスに移る橋渡しです
上手く地声からミックスボイスに移れる人は、常に5.5くらいの息の量(声帯閉鎖)で歌って、5.7→6→6.5など、さらに微妙に声帯閉鎖をコントロールします
例えば6の息の量なら強いミックスボイス。6.5なら弱いミックスボイス。7になると息混じりのファルセット。みたいな感じです
注意点
リップロールは小刻みに唇をプルプルさせるのが正解で、ブルン!ブルン!とさせるのは間違いです。これは8~10の息が出ているので多すぎです
唇を固く閉じて「ぶぶぶーー」とやるのも間違いです
目安として、15秒~30秒くらいプルプルさせてください
「ブルン!ブルン!」だと10秒くらいで肺の息が全部出てしまいます
「ぶぶぶーー」だと息を止めてる状態と変わらないので、30秒経っても肺に息が残ってると思います
あと、声帯閉鎖が弱く、ファルセットみたいに息がスカスカ抜けてしまう人は、リップロール練習は逆効果になるかもしれません
声帯閉鎖が強い人には、良い練習になると思います
「ハミングじゃダメなの?」と思うかもしれませんが、ハミングとリップロールは目的が違う練習です。ハミングは声帯閉鎖を強くした状態でもできるからです
個人的には、ハミングやストローエクササイズは、少ない息の量で行うエクササイズ。リップロールやタントリルは多い息の量で行うエクササイズだと思ってます
ストローエクササイズについては→こちら
「リップロールをやらなくても、裏声やファルセットで歌えば声帯閉鎖が弱まるのでは?」とのご意見もあるかもしれません。それも一理あります
リップロールで歌うトレーニングの良いところは、唇が抵抗になって呼気が少しせき止められ、声帯にバックプレッシャー(空気の圧力)がかかって声帯振動を整える点です
さらに、呼気がせき止められるので、声帯はリラックスしながらも、一定の量の息を安定して吐かないと、リップロールは上手くできません
ファルセットだと、モワッと何の抵抗もなく息が出てしまい、呼吸の練習にはなりません
裏声は声帯に負担をかける場合もあるので、多用するのは良くないです
一番の問題は、リップロールが出来ない人がいることです・・・
唇の両端をちょっと持ち上げるとプルプルしやすくなります
あと、唇が濡れているほうがプルプルしやすいので、風呂場なんかで練習すると良いです